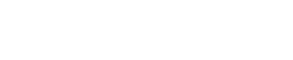2025.10.01地質調査の方法とは?主な調査手法と特徴を徹底解説
建物や道路、橋梁などの工事を行う際に欠かせないのが「地質調査」です。
地盤の強さや性質を正確に把握することで、安全性の高い設計や施工が可能になります。
しかし、地質調査にはさまざまな方法があり、精度やコスト、調査できる深さが異なります。
この記事では、代表的な地質調査の方法やそれぞれの特徴、コストと精度のバランス、そしてどの方法を選ぶべきかの基準についてわかりやすく解説します。
地質調査の主な種類とそれぞれの特徴
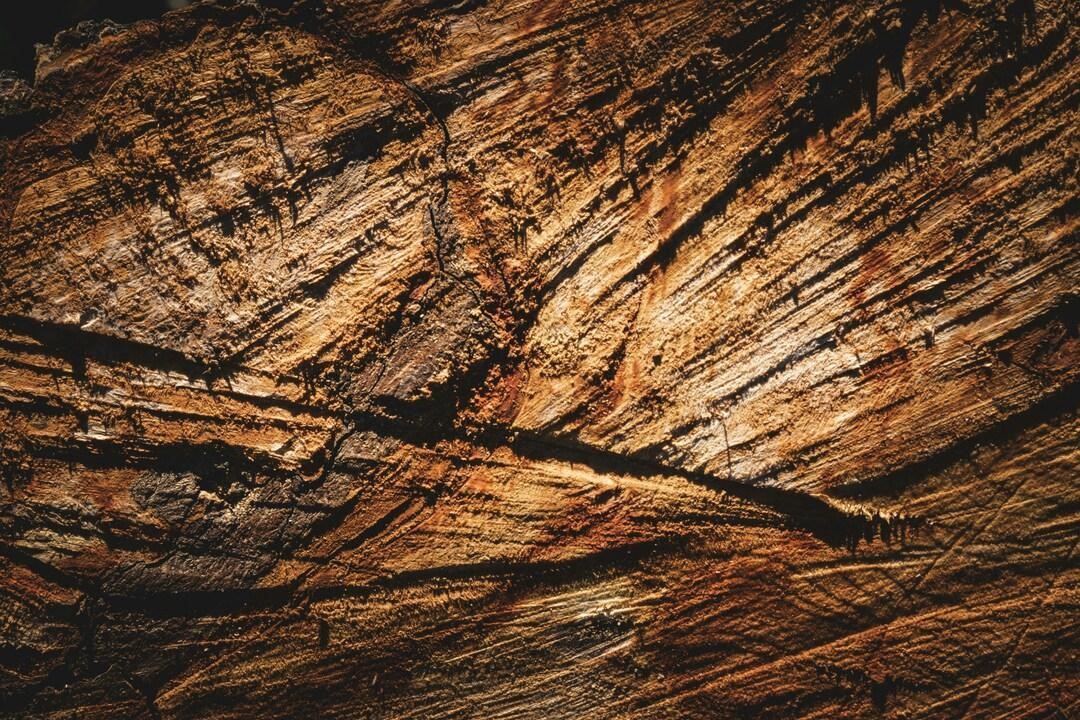
地質調査には、大きく分けて次の3つの方法があります。
物理調査(地表から非破壊で調べる方法)
地震波や電気抵抗を利用して地盤の性質を調べる方法です。
大規模な敷地や道路建設の際に使われ、広範囲を短期間で調査できるのが特徴です。
・地震波探査
地表で人工的に振動(ハンマー打撃や小型発破など)を与え、その伝わり方を観測する方法です。
特に、地震工学的な評価や液状化の可能性を検討する際に活用されます。
・電気探査
地盤に電流を流し、電気抵抗の分布を測定することで、地盤の構造や地下水の有無を推定します。
水分を多く含む地層は電気を通しやすいため、地下水位や透水性の把握に有効です。
ただし、どちらの探査方法も結果は推定値にとどまることが多く、精度は限定的になります。
スクリューウエイト試験(地盤の硬さを測定する方法)
地中にロッドを押し込み、その抵抗から地盤の強さを測る方法です。
住宅建築などの小規模な工事でよく用いられます。
スクリューウエイト試験は、コストと時間を抑えつつ、住宅レベル(浅い地層)の地盤情報を得るための手法として非常に有効です。
ただし、地盤条件が複雑な場合や重い建物の場合は、ボーリングなど詳細調査と組み合わせて使用するのが一般的になります。
ボーリング調査(試料を採取し地層を直接確認する方法)
掘削によって実際に土や岩を取り出し、地層の構成を直接確認できる方法です。
精度が高く、建物の基礎設計に欠かせませんが、コストと時間がかかるのが難点です。
スクリューウエイト試験とは

SWS試験は、ロッドの先端にスクリュー状の部材を取り付け、回転や荷重を加えて地盤に捩じ込み、その抵抗値を測定する方法です。
深さ10m程度まで調査可能で、戸建住宅や小規模建築で多用されます。
メリット
・調査費用が比較的安い
・短時間で結果が得られる
・軟弱地盤の判定に有効
スクリューウエイト試験(SWS)の大きなメリットは、比較的低コストで調査を行える点にあります。
専用機器を用いて地盤にロッドを押し込む簡易的な手法のため、施工期間も短く、短時間で結果を得ることが可能です。
これにより、小規模な住宅建築や軽量構造物の基礎設計の際に、手軽に地盤の硬さや軟弱地盤の有無を確認することができます。
デメリット
・深部の地層まで把握しにくい
・土質(粘土か砂かなど)までは正確に判別できない
SWS試験には、限界もあります。
試験は浅い地盤を対象とすることが多く、深部の地層の状態までは把握しにくい点が挙げられます。
また、土質の詳細、例えば粘土か砂かといった具体的な分類までは正確に判別できないため、より精密な設計や大規模建築物の基礎設計では、別途ボーリング調査などの詳細調査が必要になる場合があります。
そのため、SWSは「手軽さとコストの低さ」を活かしつつ、必要に応じて他の調査手法と組み合わせて使うのが効果的です。
ボーリング調査の流れとメリット

1.ボーリング機械を設置
調査位置の測量やマーキングを行い、信頼できる試料・データを得るための基盤づくりを行います。
設計上重要な柱や荷重集中位置を優先的にします。
2.掘削しながら土や岩を採取
地層に応じたビットを選定し、トルク・回転数。泥水性状(比重・粘性)を管理し、実試料を確実に回収します。
3.N値試験(標準貫通入試験)を実施
サンプラーを打ち込むときの打撃回数(N値)にて、砂・粘土等の相対的な硬さ/締まり具合を定量評価します。
4.試料を室内で分析し、土質・含水比・強度を判定
採取した試料を用いて、設計に必要な数値(パラメータ)を確定し、地盤モデルを構築を行い、工事可能かの判定に利用されます。
ボーリング調査は、地盤の性質を直接確認できる最も信頼性の高い方法の一つです。
現場に専用のボーリング機械を設置し、掘削を進めながら一定の深さごとに土や岩を採取します。
掘削の過程では「標準貫入試験(N値試験)」が行われ、地盤の硬さを数値で測定できます。
その後、採取した試料は室内試験に回され、土質、含水比、せん断強度などを分析し、地盤の性質を多角的に評価を行います。
ボーリング調査で分かること
ボーリング調査によって得られる情報は多岐にわたります。
代表的なものとして、地層の構成や層厚、N値による地盤の強さ、地下水位の位置などがあります。
さらに、地震時の液状化リスクを評価できるのも大きな特徴です。
これらのデータは、基礎の形状や補強方法を検討するうえで欠かせない要素であり、建築物や構造物の安全性に直結します。
メリットとデメリット
ボーリング調査の最大のメリットは、精度の高いデータが得られることです。
実際の土や岩を採取し、数値化したデータを基に設計できるため、不同沈下や地盤トラブルを未然に防げます。
その一方で、機械や人員が必要なため調査費用は高額になり、掘削や試験に時間がかかる点がデメリットといえます。
小規模建築では負担が大きいため、必要に応じてSWSなどの簡易調査と使い分けるのが一般的です。
調査の精度とコストのバランスの取り方

地質調査では、「どこまで精度を高めるべきか」と「どの程度の費用をかけるべきか」のバランスを取ることが非常に重要です。
小規模建築と大規模建築で必要な調査レベルの違い
・戸建住宅:SWSで地耐力を把握
・中高層ビル/橋梁:ボーリングで詳細データを取得
調査を簡易に済ませれば初期費用は抑えられますが、地盤条件を正しく把握できないと不同沈下や基礎補強工事が後から必要となり、結果的に大きなコスト増につながるリスクがあります。
逆に、必要以上に精度の高い調査を行えば無駄なコストをかけてしまう可能性もあります。
そのため、建築物の規模や用途、敷地の地盤条件を考慮して最適な調査方法を選定することが求められるのです。
調査が不十分だと、不同沈下や基礎補強の追加工事が発生し、結果的にコスト増加につながる可能性があります。
どの方法を選ぶべき?選定の基準と事例

地質調査の方法は、建築物の規模や用途、また建設予定地の地盤条件によって選び方が変わります。
さらに、実務では「SWS」と「ボーリング」をうまく組み合わせて、コストと精度のバランスをとることも一般的です。
以下に、主な選定基準を整理します。
建築物の規模や用途による選び方
建物の規模が小さいか大きいかによって、必要な調査精度は大きく異なります。
・木造2階建て住宅などの小規模建築物
建物の荷重が比較的軽いため、浅い地盤の性状を確認できるSWSで十分対応可能です。
調査費用を抑えつつ、短期間で結果を得られるのがメリットになります。
・鉄筋コンクリート造マンションや商業施設などの大規模建築物
建物の重量が大きいため、浅層の調査だけでは安全性を担保できないです。
そのため、ボーリング調査を実施し、深部までの地層構成や地盤強度を正確に確認する必要があります。
地盤条件による選び方
同じ規模の建物でも、建設予定地の地盤状況に応じて調査方法を選ぶことが重要です。
・軟弱地盤や盛土がある地域
表層だけでは判断が難しく、不同沈下や液状化のリスクを見落とす可能性があります。
そのため、ボーリング調査を行い、深い地層や地下水位まで調べるのが適切です。
・比較的安定した地盤が期待できる地域
SWS調査で地盤の硬さを確認するだけで十分なケースも多いです。
短時間で施工可能かどうかの判断が可能であり、工期短縮に繋げることができます。
実際の調査組み合わせ事例
実務では「まず簡易調査→必要に応じて詳細調査」という流れが多く採用されています。
1. 最初にSWSで簡易調査
数か所を短時間で調べ、地盤の全体像を把握します。
コストを抑えて初期段階の判断が可能です。
2. 問題が見つかったらボーリング調査を追加
地盤が軟弱であったり、地下水位の影響が疑われる場合に実施します。
詳細なデータを見て、設計に直結させることができます。
このように、両者を組み合わせることで「コスト削減」と「精度確保」の両立が可能になります。
特に、中規模以上の建築プロジェクトでは、このアプローチが効率的かつ現実的です。